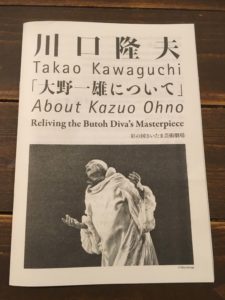DETAIL
川口隆夫『大野一雄について』、『ゲンロン5 幽霊的身体』、「自然」と「作為」から見る日本コンテンポラリーダンス
川口隆夫を見たことも、大野一雄を見たこともないので、前触れの大野一雄の「完コピ」がどこまでできているのかは定かではないが、そこにしっかりと現前するパフォーマーがいることは、晴れた彩の国さいたま芸術劇場入り口の大階段で、スマホ片手に移動する観客に囲まれながら、冬の西日を浴び汗ばむローラーブレードを履いたおっさん(口が悪くてスミマセン!本人を見たことがなかったので最初目にした時の感想です)を目視した時に分かった。
作品全体としては、当時の土方巽の演出がどこまで動きを固めていたのかは定かではないが、ガチガチにカウントにはめた作り方はしていなかったであろうと予測できるので、即興と振付の面白い関係性の検証であり、また自分の目でこの作品を見て、何故海外にこの作品が多く呼ばれるのかが良くわかった。海外に呼ばれることが作品の目的ではないが、この作品の立ち位置が明確であるため、作品を見た後に誰かと共有、または議論したくなるのだ。そういった文脈に基づいた「語れるダンス」作品が海外では好まれるし、個人的には好きなので、少しだけ拙い文章だが書いてみようと思う。また、この文章の多くは最近読んだ『ゲンロン5 幽霊的身体』に書かれていることを引用したり、そこから関連して感じたことを書かせてもらった。
この作品を見ていてふと丸山眞男の「自然」(じねん)と「作為」(さい)という言葉が浮かび上がった。この二つの対立する理念は、文化的外圧に対する受容史として見られる日本文化史で度々使われる概念である。丸山は日本思想の「古層」において、構築的で発展的な「作為」の原理よりも、おのずからなるにまかせる「自然」の原理が常に優越していると批判的に指摘した。[★1] ダンスでいうとバレエには「パ」があり基本的にパの「構築」によりバレエはできているので「作為」の概念で作られていると言える。それに対して舞踏は(舞踏の研究をしているわけでもなく、舞踏家ではないので間違いでしたらご指摘下さい)、ダンサーにイメージや概念を伝えて個人から滲み出て来るものを掬い上げ、その解釈を各々ダンスに変換していく。内側から「生成」されるムーヴメントによってダンスが作られていくわけなので「自然」となる。丸山の指摘は物凄く簡単に言うと、作為は西洋的で構築されているもので、自然は日本的で生成されているものである。そして、西洋は作為を、日本は自然を大切にする傾向が強い、と言う指摘だ。だが、この作品は”舞踏作品”であるのにも関わらず、「おのずからなる」動き、言わば自然のコンセプトは一切排除されている。また、川口本人の振付やダンスも皆無ということになる。自分で作らない作品。また、「完コピ」を目的にダンスが行われているため、達成すべき「形」があり、即興や個人の解釈の余地はないからである。個人的見解だが、日本のコンテンポラリーダンスは文脈に重きは置かず、アーティスト個人の「思い」を作品にすることが多いと思う。その是非については個々に委ねるとして、考え方の提示や文脈がない限り、日本のコンテンポラリーダンスの存在は世界では語られることが少なくなってしまうである。要するに日本のコンテンポラリーダンスは世界にあってもなくても変わらないのである。現状日本ではコンテンポラリーダンスは盛んではなく、ニュースで取り上げられることもあまりない。それがダンス人口の少なさに繋がり、故に税金をかける意味合いも少ないので助成金が少なく、ダンスで食べていけないという日本のダンサーの嘆きに繋がるのである。なので、僕は冒頭で言ったように「語れるダンス」が必要だと思うし、好きだ。もちろんダンスの全てが語れるわけはなく、言葉から溢れ、はみ出ているものが大切なのは言うまでもない(でないと踊らずに本を書けば良くなってしまうので)。情熱や感情は大切だし、それがなければ作品は作れない。が、作品を観た時にどうしても「思い」だけで作っているものは、ダンス自体が素晴らしくとも強度が弱く感じてしまうのである。話が脱線してしまったが、日本で生まれたコンテンポラリーダンスのスタイルとして唯一世界で認知されている舞踏、その中でもピナバウシュをはじめ、世界に大きな影響を与えた大野一雄を完コピするというこの作品の試みは非常に面白い楔を日本コンテンポラリーダンス史に打ったと思っている。「自然」と「作為」という概念を丸山はもともと政治思想史について述べており、文化論や芸術論は関係ないのだが、今日のコンテンポラリーダンスにもこの関係性/優位性は十分に当てはまるので、ここで使わせて頂いた。
さて、川口隆夫のこの作品の仮説は、〈「形」を完璧にコピーすることができれば、「魂」もコピーすることができる〉である。その点においては肯定も否定もし難い。当時とは社会も観客もそして何よりも演者という魂の器が違うのである。そして何より魂をコピーできるかどうかは測る術がないのである。歌舞伎においては先代の芸風に似てきたというのは褒め言葉であり、彼らは「型」と「名跡」という2つのDNAを継ぐ。歌舞伎と幽霊の関係性については『ゲンロン5 幽霊的身体』にて木ノ下裕一がより詳しく書いているので、そちらを参考していただきたい。先にこの作品には達成すべき「形」があると書いたが、それはやはり「形」であって「型」ではない。川口も敢えて「型」で「形」をコピーする、と記したのもこのような理由があってのことであろうと予想している。それを「型」と呼ぶにはには年月が浅すぎるし、大野一雄本人から直接稽古を受けたわけでもなく、当時のノートなどは残っていたようだが、歌舞伎のようにしっかりとした形で棋譜が残っているわけでもないのである。歌舞伎や日舞が敢えてテクノロジーの発展した現代においても、口伝で伝えているのにもそんな理由があるのであろう。「型」まで昇華されていると、個を出す余地があるように感じられるが、「完コピ」にその余地はない。しかし逆説的に言えば、「完コピ」をしているからこそはみ出てくるものもある、という具合である。頭からつま先までの全身タイツを着ると、没個性になるどころかその人の身体が逆に浮き出てくる、という発想と同じである。しかし、「川口隆夫らしさ」という点においては、開演時刻の前から大階段で始まっていた映像作品からの引用である『O氏の肖像』が一番出ていたのではないのだろうか。映像作品の引用であるから完コピは不可能であり、そこには躍動する川口隆夫/大野一雄の体があった。劇場に入ってからの1977年『ラ・アンヘルチーナ頌』、81年『私のお母さん』、85年『死海』はビデオ音声を使っていることもあり(照明は1985年より大野一雄の照明をしていた溝端俊夫、衣装も北村教子が当時のもののレプリカとなるべくオリジナルを忠実になぞろうとしている)、音声から否応なく忍び込む大野一雄の幽霊に翻弄されてしまう。しかし、当時の雰囲気は作品に留まらず会場にも浸透しており、『O氏の肖像』では観客の投げたハローキティーの人形を咥えながら走り回る川口や、作品後には花束が文字通り投げ入れられていた。
丸山の「作為」と「自然」の話に戻るが、西洋に根付く考え方は、創造神が7日間で世界を創り上げたというものだ。要するに、主体が創意に基いて構築するという考え方だ。それに対し、八百万の神を信じ、「つくる」ことは人間主体を超えた「なる」ことに結び付けられがちであった日本には、構築的な考え方が馴染まないのも納得がいくのだが、[★2]この作品は「作為」と「自然」の架け橋になるのではないかと思った。もののけは日本人が物にも魂が宿ると信じている現れである。魂が「コピー」されたかどうかはわからないが、舞台上で着替える川口が劇場に入ってからの最初の着替えの時に鳴ったハンガーの金属音が美しく響いたところや投げ入れらる花束に、大野一雄に対する「思い」もこの作品にはしっかりと宿り、観客に伝わっていると感じた。
★1 黒瀬陽平『ゲンロン5 幽霊的身体』、(二〇一七年六月号) 二二三頁。
★2 北澤憲昭『眼の神殿 「美術」受容史ノート[定本]』、ブリュッケ、二〇一〇年 二三八頁。
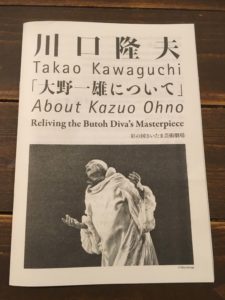

作品全体としては、当時の土方巽の演出がどこまで動きを固めていたのかは定かではないが、ガチガチにカウントにはめた作り方はしていなかったであろうと予測できるので、即興と振付の面白い関係性の検証であり、また自分の目でこの作品を見て、何故海外にこの作品が多く呼ばれるのかが良くわかった。海外に呼ばれることが作品の目的ではないが、この作品の立ち位置が明確であるため、作品を見た後に誰かと共有、または議論したくなるのだ。そういった文脈に基づいた「語れるダンス」作品が海外では好まれるし、個人的には好きなので、少しだけ拙い文章だが書いてみようと思う。また、この文章の多くは最近読んだ『ゲンロン5 幽霊的身体』に書かれていることを引用したり、そこから関連して感じたことを書かせてもらった。
この作品を見ていてふと丸山眞男の「自然」(じねん)と「作為」(さい)という言葉が浮かび上がった。この二つの対立する理念は、文化的外圧に対する受容史として見られる日本文化史で度々使われる概念である。丸山は日本思想の「古層」において、構築的で発展的な「作為」の原理よりも、おのずからなるにまかせる「自然」の原理が常に優越していると批判的に指摘した。[★1] ダンスでいうとバレエには「パ」があり基本的にパの「構築」によりバレエはできているので「作為」の概念で作られていると言える。それに対して舞踏は(舞踏の研究をしているわけでもなく、舞踏家ではないので間違いでしたらご指摘下さい)、ダンサーにイメージや概念を伝えて個人から滲み出て来るものを掬い上げ、その解釈を各々ダンスに変換していく。内側から「生成」されるムーヴメントによってダンスが作られていくわけなので「自然」となる。丸山の指摘は物凄く簡単に言うと、作為は西洋的で構築されているもので、自然は日本的で生成されているものである。そして、西洋は作為を、日本は自然を大切にする傾向が強い、と言う指摘だ。だが、この作品は”舞踏作品”であるのにも関わらず、「おのずからなる」動き、言わば自然のコンセプトは一切排除されている。また、川口本人の振付やダンスも皆無ということになる。自分で作らない作品。また、「完コピ」を目的にダンスが行われているため、達成すべき「形」があり、即興や個人の解釈の余地はないからである。個人的見解だが、日本のコンテンポラリーダンスは文脈に重きは置かず、アーティスト個人の「思い」を作品にすることが多いと思う。その是非については個々に委ねるとして、考え方の提示や文脈がない限り、日本のコンテンポラリーダンスの存在は世界では語られることが少なくなってしまうである。要するに日本のコンテンポラリーダンスは世界にあってもなくても変わらないのである。現状日本ではコンテンポラリーダンスは盛んではなく、ニュースで取り上げられることもあまりない。それがダンス人口の少なさに繋がり、故に税金をかける意味合いも少ないので助成金が少なく、ダンスで食べていけないという日本のダンサーの嘆きに繋がるのである。なので、僕は冒頭で言ったように「語れるダンス」が必要だと思うし、好きだ。もちろんダンスの全てが語れるわけはなく、言葉から溢れ、はみ出ているものが大切なのは言うまでもない(でないと踊らずに本を書けば良くなってしまうので)。情熱や感情は大切だし、それがなければ作品は作れない。が、作品を観た時にどうしても「思い」だけで作っているものは、ダンス自体が素晴らしくとも強度が弱く感じてしまうのである。話が脱線してしまったが、日本で生まれたコンテンポラリーダンスのスタイルとして唯一世界で認知されている舞踏、その中でもピナバウシュをはじめ、世界に大きな影響を与えた大野一雄を完コピするというこの作品の試みは非常に面白い楔を日本コンテンポラリーダンス史に打ったと思っている。「自然」と「作為」という概念を丸山はもともと政治思想史について述べており、文化論や芸術論は関係ないのだが、今日のコンテンポラリーダンスにもこの関係性/優位性は十分に当てはまるので、ここで使わせて頂いた。
さて、川口隆夫のこの作品の仮説は、〈「形」を完璧にコピーすることができれば、「魂」もコピーすることができる〉である。その点においては肯定も否定もし難い。当時とは社会も観客もそして何よりも演者という魂の器が違うのである。そして何より魂をコピーできるかどうかは測る術がないのである。歌舞伎においては先代の芸風に似てきたというのは褒め言葉であり、彼らは「型」と「名跡」という2つのDNAを継ぐ。歌舞伎と幽霊の関係性については『ゲンロン5 幽霊的身体』にて木ノ下裕一がより詳しく書いているので、そちらを参考していただきたい。先にこの作品には達成すべき「形」があると書いたが、それはやはり「形」であって「型」ではない。川口も敢えて「型」で「形」をコピーする、と記したのもこのような理由があってのことであろうと予想している。それを「型」と呼ぶにはには年月が浅すぎるし、大野一雄本人から直接稽古を受けたわけでもなく、当時のノートなどは残っていたようだが、歌舞伎のようにしっかりとした形で棋譜が残っているわけでもないのである。歌舞伎や日舞が敢えてテクノロジーの発展した現代においても、口伝で伝えているのにもそんな理由があるのであろう。「型」まで昇華されていると、個を出す余地があるように感じられるが、「完コピ」にその余地はない。しかし逆説的に言えば、「完コピ」をしているからこそはみ出てくるものもある、という具合である。頭からつま先までの全身タイツを着ると、没個性になるどころかその人の身体が逆に浮き出てくる、という発想と同じである。しかし、「川口隆夫らしさ」という点においては、開演時刻の前から大階段で始まっていた映像作品からの引用である『O氏の肖像』が一番出ていたのではないのだろうか。映像作品の引用であるから完コピは不可能であり、そこには躍動する川口隆夫/大野一雄の体があった。劇場に入ってからの1977年『ラ・アンヘルチーナ頌』、81年『私のお母さん』、85年『死海』はビデオ音声を使っていることもあり(照明は1985年より大野一雄の照明をしていた溝端俊夫、衣装も北村教子が当時のもののレプリカとなるべくオリジナルを忠実になぞろうとしている)、音声から否応なく忍び込む大野一雄の幽霊に翻弄されてしまう。しかし、当時の雰囲気は作品に留まらず会場にも浸透しており、『O氏の肖像』では観客の投げたハローキティーの人形を咥えながら走り回る川口や、作品後には花束が文字通り投げ入れられていた。
丸山の「作為」と「自然」の話に戻るが、西洋に根付く考え方は、創造神が7日間で世界を創り上げたというものだ。要するに、主体が創意に基いて構築するという考え方だ。それに対し、八百万の神を信じ、「つくる」ことは人間主体を超えた「なる」ことに結び付けられがちであった日本には、構築的な考え方が馴染まないのも納得がいくのだが、[★2]この作品は「作為」と「自然」の架け橋になるのではないかと思った。もののけは日本人が物にも魂が宿ると信じている現れである。魂が「コピー」されたかどうかはわからないが、舞台上で着替える川口が劇場に入ってからの最初の着替えの時に鳴ったハンガーの金属音が美しく響いたところや投げ入れらる花束に、大野一雄に対する「思い」もこの作品にはしっかりと宿り、観客に伝わっていると感じた。
★1 黒瀬陽平『ゲンロン5 幽霊的身体』、(二〇一七年六月号) 二二三頁。
★2 北澤憲昭『眼の神殿 「美術」受容史ノート[定本]』、ブリュッケ、二〇一〇年 二三八頁。